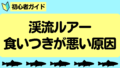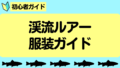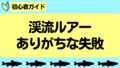原二旅 釣り部
ゼロから始める、渓流ルアー釣り
初心者による、初心者のための完全ロードマップ
カテゴリー別に記事を探す
Step 1
基礎知識
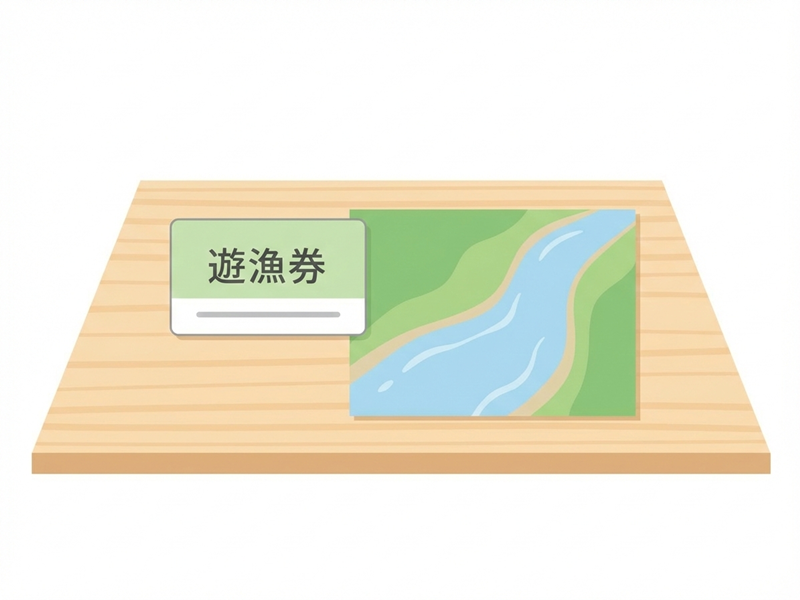
Step 2
道具・装備選び

Step 3
実釣テクニック

お小遣いで買える装備で、最高の冒険へ
道具の値段と、渓流の楽しさは比例しません。「高い道具じゃなきゃダメ?」と不安だった頃の自分に教えたい、2年生になった今でも愛用している「安くて最高の相棒たち」を紹介!


釣果の向こう側へ。
エッセイ・釣行記(note)
釣果よりも大切にしたいものがある。
ブログでは書ききれない個人的な思考や、釣行の思い出、ハンドメイドルアーへの想いは、noteに綴っています。