
ラインってどう選べば良いの?
PEとかナイロンとかフロロとか…聞くけど。

結論から言うと、初心者はナイロン4ポンドがおすすめ!
渓流ルアーフィッシングを始めたばかりの方にとって、「ライン選び」は意外と悩ましいポイントです。
釣具店に行けば、ナイロン・フロロカーボン・PEなど、さまざまな種類のラインが並んでいて、どれを選べばいいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか?
実は、ラインの種類によって「強さ」「感度」「トラブルの起きにくさ」などが大きく異なり、釣果やストレスの少なさに直結します。
この記事では、渓流ルアー釣りで使われる代表的な3種類のラインの違いや、初心者におすすめの選び方、太さや長さの目安まで、わかりやすく解説します。
迷いがちなライン選びですが、基本を押さえればもう悩む必要はありません。
渓流ルアーに使う「ライン」とは?
渓流ルアーフィッシングでは、「ロッド」「リール」「ルアー」に注目が集まりがちですが、実は「ライン(釣り糸)」も釣果を大きく左右する重要な要素です。
ルアーの操作性や感度、トラブルの起きやすさにまで関わってくるため、適切なライン選びは快適な釣りの第一歩と言えるでしょう。
ここでは渓流ルアーにおけるラインの役割と重要性、そしてなぜライン選びが大切なのかについて解説します。
ラインの役割と重要性
釣りにおける「ライン」は、ロッドとルアー、そして魚をつなぐ大切な要素です。
渓流ルアーフィッシングでは、ラインの選び方によってルアーの飛距離、操作性、魚の反応、さらにはキャッチ率までも大きく左右されます。
たとえば水流の速い場所では、ラインが水に流されて思うようにルアーが動かせなかったり、細すぎるラインだと大物がかかったときに切れてしまうこともあります。
一方で太すぎると魚に警戒されてしまったり、キャストの飛距離が落ちてしまうデメリットもあります。
つまり、「どんな川で、どんなルアーを、どんな魚に向けて使うのか」を考えながら、適切なラインを選ぶことがとても重要です。

「渓流」と一言で言っても、色々な渓流があります。
なので基本的な考え方を中心に紹介しますよ!

極端に言えば源流のイワナやヤマメと、本流のサクラマスじゃ大きく違うわよね…。
なぜ“ライン選び”が重要なのか
初心者のうちは「ラインはとりあえず適当でいいや」と考えてしまいがちですが、それは非常にもったいない選択です。
ラインは目立たない存在に思えるかもしれませんが、実は「ルアーがきちんと泳ぐか」「アタリが感じ取れるか」「魚を確実に取り込めるか」に大きく影響しています。
また、渓流では障害物(岩・木・流木)も多く、ラインに擦れやすい環境です。
そうした条件に強いラインを選ばなければ、せっかくのヒットを逃してしまうことにもつながります。
「適切なライン選び」こそ、渓流ルアー釣りの快適さと釣果に直結する、最も基本的で重要な準備のひとつです。

ライン大事!
じゃあどう選ぶのか?を続けて紹介していきます。
渓流釣りで使われる3種類のラインの特徴

渓流ルアーで使われるラインには、大きく分けて以下の3種類があります。
- ナイロンライン
- フロロカーボンライン
- PEライン
それぞれに特徴や向き不向きがあるため、釣り場の条件や経験値に応じて使い分けるのが理想です。
ここでは各ラインのメリット・デメリットを初心者向けにわかりやすく解説します。
ナイロンラインの特徴とメリット・デメリット
柔らかくしなやかで、扱いやすさに優れるラインです。
トラブルが少なく、渓流釣り初心者には特におすすめされています。
メリットとしては
- 巻きグセがつきにくく、トラブルが少ない
- しなやかでキャストしやすい
- 比較的安価で入手しやすい
- 水に浮きやすく、流れの変化が見やすい
といったところ。
逆にデメリットとしては
- 擦れに弱く、根ズレや岩などに当たると劣化しやすい
- 吸水性があり、長時間使うと劣化しやすい
- 感度がやや低く、繊細なアタリが取りにくい場合も
となります。

ナイロンは初めての渓流ルアー…と言うより、「初めて釣りをする人」におすすめ。
初心者でも扱いやすい!

トラブルが少ないのが特徴ね。
フロロカーボンラインの特徴とメリット・デメリット
硬めで感度が高く、沈みやすい素材です。
根ズレにも強く、岩の多い渓流でも安心感があります。
メリットとしては
- 擦れに強く、根ズレ対策になる
- 感度が高く、アタリが取りやすい
- 水に沈みやすく、ルアーが自然に流れる
といったところ。
逆にデメリットは
- 硬くて巻きグセがつきやすく、扱いにくいことも
- ナイロンより高価
- スピニングリールだと糸ヨレしやすい場合がある
となります。

渓流でフロロを使う人はあまりいない印象です。
擦れに強いので、PEのリーダーとして使うのが一般的かな。

「リーダー」については後ほど解説するわ。
PEラインの特徴とメリット・デメリット
細くて強度が高く、遠投や繊細なアクションが得意。
しかし、渓流で使うには工夫が必要です。
メリットとしては
- 同じ強度なら最も細くでき、飛距離が出る
- 感度が高く、小さなアタリも明確に伝わる
- 劣化しにくく、長く使える
といったところ。
逆にデメリットは
- 擦れに非常に弱く、岩場に不向き
- ノット(結束)やリーダーが必要で扱いが難しい
- 風に弱く、軽いルアーでは流されやすい
となります。

昔に比べるとかなり扱いやすくなったようで、今は最初からPEを勧める専門書も増えてます。
それだけメリットがデカいと言うか…強い!

リーダーを結ぶことに抵抗がなければ…って感じかしら?
渓流ルアー初心者におすすめのラインは?
渓流ルアー釣りを始めたばかりの方にとって、「どのラインを選ぶべきか」は最初の大きな悩みのひとつです。
ここでは初心者が扱いやすく、かつ釣果も期待できるライン選びのポイントを紹介します。

先ほど紹介した3種類のラインの特徴を踏まえて、初心者が考慮するべきポイントを紹介します!
選びやすさ・扱いやすさで考える
まず重視したいのは「扱いやすさ」です。
キャスト時のトラブルが少なく、ルアーの動きも素直に伝わるナイロンラインは、初心者にとって非常に心強い存在です。
柔らかくてクセが付きにくく、結びやすいためライントラブルのリスクを減らすことができます。
一方、フロロカーボンラインは硬くて扱いにくい面があり、特にスピニングリールでのライントラブルが起こりやすいというデメリットがあります。
PEラインも扱いに注意が必要で、初心者には少しハードルが高いと言えるでしょう。
コスパ・耐久性・感度のバランス
ナイロンラインはコストパフォーマンスにも優れています。
万が一トラブルでラインを切ってしまっても、経済的な負担は少なめです。
耐久性や感度の面では他のラインに劣るものの、まずは快適に釣りを楽しむことが最優先であれば、十分な性能と言えます。
フロロやPEラインは高性能ではありますが、価格や扱いやすさとのバランスを考えると、最初の1本としてはややオーバースペックな場合もあります。
結論:まずは「ナイロンライン」から始めよう
これらを総合的に判断すると、渓流ルアー釣りの初心者には「ナイロンライン」がおすすめです。
まずはナイロンラインで釣りの基本を身につけ、慣れてきたら釣り場やターゲットに応じてフロロやPEを使ってみるのが良いでしょう。

ラインは消耗品なので、とりあえずナイロンで初めて…劣化したら違うのを試してみるのもおすすめ。

ナイロンは蜘蛛の巣に強いのもメリットね。
ラインの太さ・号数・長さの目安とは?
ラインの種類を決めたら、次は「どのくらいの太さや長さにすればいいのか?」が気になるところです。
ここでは渓流ルアーに適したラインの目安を紹介します。
渓流で使うラインの“標準的な太さ”は?
初心者がナイロンラインを選ぶ場合、4lb(ポンド)前後が目安になります。
日本式の号数でいうと、1号前後が一般的です。
あまり細すぎると切れやすく、太すぎるとキャストやルアーの操作に影響が出てしまいます。
最初は「迷ったら4lb(約1号)」という基準で選ぶと失敗が少ないです。

lbと号は必ずしもイコールではないのですが…とりあえず「4lb=1号」と覚えてOKです。
長さはどのくらい巻けばいい?
スピニングリールに巻く長さは、最低でも70~100mは欲しいところです。
実際には渓流で100m以上ラインを出すことはほぼありませんが、トラブルやラインの劣化を考えると、余裕をもって巻いておくのが安心です。
リールに適正ライン量の目盛りがある場合は、それを参考に巻くようにしましょう。

逆に言うと100mくらいしか不要なので、リールはシャロースプールがおすすめ。

リールの話は下記の記事を読んでね。
細すぎ・太すぎはNG?トラブルを防ぐために
細いラインは飛距離や食わせ能力に優れていますが、障害物との擦れに弱く切れやすいというリスクがあります。
逆に太すぎるラインは、魚に警戒されやすく操作性や飛距離も落ちるため、釣果に悪影響を及ぼします。
川の環境や対象魚のサイズに合わせて、バランスの良い太さを選ぶことが重要です。
迷ったら「基準の太さ(ナイロンで4lb)」を使い、実釣を重ねながら微調整していくと良いでしょう。

ナイロン4lbはあくまでも基本。
尺(約30cm)ヤマメやイワナは十分対応可能ですが、北海道のように50cmオーバーのニジマスやブラウンがいるところはもう少し太くしたいですね。

逆に20cmくらいがメインなら3lbとかに下げるのもアリってことね。
よくある質問(FAQ)
ここでは初心者の方がよく悩みがちなポイントをQ&A形式でまとめました。
釣具選びで迷ったときの参考にしてください。
リーダーは必要?ラインとどう違う?
PEラインを使う場合、ナイロンやフロロの「リーダー」を結ぶのが基本です。
リーダーはルアーに近い部分に付ける補助ラインで、擦れ対策や結束の強度を高めるために使われます。
ナイロンやフロロメインの釣りでは、特別な理由がない限りリーダーは不要です。
スピニングリールとベイトリールでラインは変わる?
基本的な選び方は共通ですが、リールのタイプによって向いているラインがあります。
- スピニングリール: ナイロン・PE・フロロいずれも使えるが、ナイロンが最も扱いやすい
- ベイトリール: フロロカーボンとの相性が良い。PEラインはバックラッシュ対策が必要
渓流ではスピニングリールを使う人が多く、初心者はまずスピニング+ナイロンの組み合わせが無難です。
カラーは何色が良い?魚に見えない色はある?
ラインのカラーは、見えにくい=釣れるというわけではありません。
むしろ、「見えやすいカラー」で人間がラインの動きを把握することの方が重要です。
初心者はライトグリーンやピンクなどの視認性の高い色を選ぶと、ルアーの位置やアタリがわかりやすくなり、釣果にもつながります。
まとめ
渓流ルアーにおけるライン選びは、釣果を大きく左右する重要なポイントです。
初心者のうちはナイロンラインを選び、太さは4lb前後、長さは100m前後を目安にすると、トラブルが少なく安心して釣りが楽しめます。
ラインの違いや特徴を理解し、実際に釣りをしながら自分に合ったスタイルを見つけていくことが、渓流ルアーフィッシングの醍醐味でもあります。
まずは“迷わない選択”から始め、釣りをしながら自分の好みを探していくのがおすすめです。

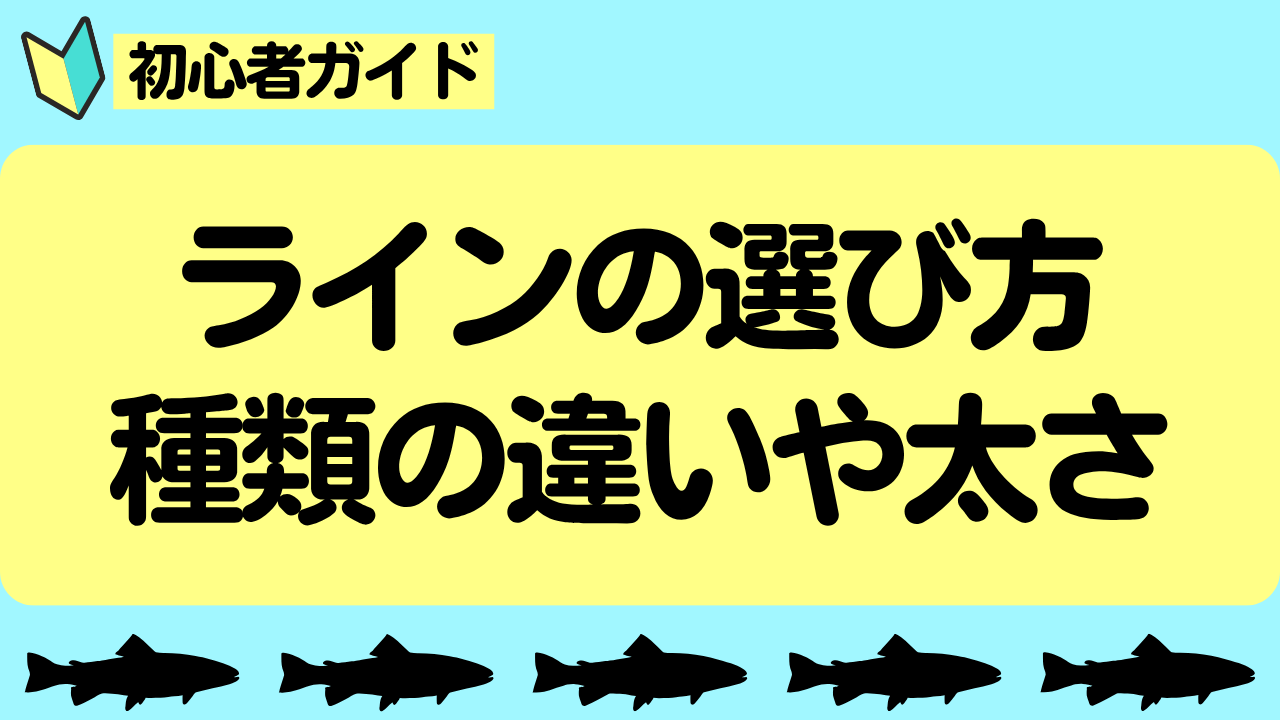

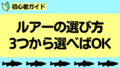
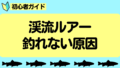
コメント